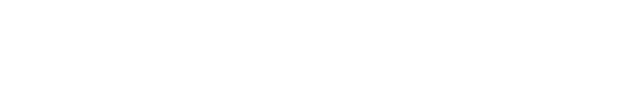整形外科
整形外科とは
整形外科とは、背骨・手・足などの運動器を造っている骨・関節・軟骨・筋・靭帯・神経等の病気やケガ等を治療します。そして単に病気やケガを治すだけでなく、歩く、走る、食事をするといった身体機能を回復させ、日常生活、社会生活への復帰を目的としています。リハビリテーションとの連携が重要です。
人が立つ、歩く、手を使う等の動作を行うための器官を運動器といいます。運動器には、骨・軟骨、筋、関節、靱帯、神経等が含まれます。整形外科は、これら運動器の病気やケガを診療します。頸が痛い、手がしびれる、腰が痛い、肩・膝などの関節の痛み・腫れ等の症状や歩行時にふらつく、手・足に力が入らないといった諸症状でお悩みの方は、整形外科を受診して下さい。切り傷や捻挫、打撲等日常的なケガから重度の背骨の疾患、関節疾患まで病院との連携を図りながら診療させて頂きます。
高齢化が進み、骨が脆くなって骨折しやすくなる骨粗鬆症を改善することは、介護無しで自立した生活を維持するためには重要です。最新の骨密度測定器機を導入し、骨粗鬆症の薬物療法に積極的に取り組んでいます。
運動器障害により立つ、歩くといった移動機能が低下するロコモーティブシンドローム(ロコモ)は、新しい疾患概念です。ロコモにより介護が必要となる、、寝たきりの生活となる事を予防するため、リハビリテーションによる運動機能の改善にも取り組んでいます。
- 1. 脊椎の疾患
- 4. 肩の疾患
- 5. 手・肘の疾患
- 2. 腰の疾患
- 3. 全身の疾患
- 7. 肘の疾患
- 6. 股関節の疾患
- 8. 足の疾患
- 9. 交通事故